
2025年3月
「逆境をバネに進化する酵母の生存戦略」
~時間をかけて強くなる不思議な生物~(後編)
後編では、井沢教授に酵母のさらなる魅力について語っていただきました。
酵母は自ら作り出したエタノールストレスによりダメージを受けるわけですが、それでもなお、必死に耐えながらエタノールを作り続けます。
そこには、どのような生存戦略が機能しているのでしょうか。井沢先生に解説いただきながら、まるで人間のようにふるまう酵母の面白い魅力について、たっぷりと語っていただきます。
酵母の生存戦略は大胆に切り替わる
通常、酵母は高いエタノール濃度に突然さらされると、すぐに死んでしまいます。ですが低いエタノール濃度で発酵することから始めて、そこからジワジワと慣らしていくと、最終的には高いエタノール濃度に耐え、生存することができます。
いったい何故でしょうか。

酵母が発酵してエタノールストレスが増えていく過程を研究していると、面白い事実がどんどんわかってきました。
キーワードは「レジリエンス」と「発酵時間」にあります。
それでは酵母の中で一体どのようなことが起きているか見ていきたいと思います。
酵母が発酵するとジワジワとエタノールが作られ、それに合わせて前編でお伝えしたように、たんぱく質に異変が起きます。Ded1という酵母にとって重要なたんぱく質が、正常な構造を維持できなくなり、凝集し始めていくのです。
凝集とは・・・たんぱく質が、異常な形で折りたたまれ、塊となって機能しなくなる現象

(Ded1が凝集している様子)
一見、Ded1が凝集していくことは、ネガティブなことのように感じますが、実は、酵母がエタノールストレスの中で生存するために戦略を変えたという見方もできるのです。
時間をかけて様子を見ていると、Ded1が機能しなくなったことにより、普段は押さえ込まれていた別の部隊が、起動し始める様子を観察できます。
まず、エタノールストレスにさらされるとstress granuleなど普段は見ることのできない構造物ができ始めます。これは、凝集して使えなくなったDed1を、一時的に保管するスペースとなります。そして、この保管スペースにDed1を修復するためのたんぱく質が登場し、応急処置を行い始めるのです。
そのほかにも、さまざまな細胞内機能の回復に向けてはたらくたんぱく質や、より耐性を強化する防御系のたんぱく質など、普段はベンチに控えていたたんぱく質が、次から次へと登場してくるのです。これは非常に興味深い現象です。

(学生たちが研究をしている様子)
これにより、応急処置、機能の復旧、耐性の強化が行われ、より強靭な酵母へと変わっていくわけです。
反対に、エタノールストレスにさらされた状態で、Ded1が凝集せずにいつまでもでしゃばっていては、これらの対処を行うことができません。
時間をかけて酵母は強くなっていく
さらに面白い点は、これらのレジリエンスは一度に発動するわけではなく、時間の経過に沿って順番に発動していく点です。
エタノールストレスにさらされた直後は、応急処置の機能が発動し、落ち着いてきたら、復旧作業の機能が発動します。そして最後は耐性強化のための機能が発動していきます。

(時間の経過とともに様々な物質が出現し酵母の生存を支えている)
これは、我々の社会とよく似ているように思えませんか?
たとえば、災害など緊急事態が発生した場合は、まずは消防車などが出動して、現場を治めようと努めます。その次は別の部隊が出動し、壊れた橋の復旧など、日常を取り戻すための作業が行われ、そして最後に、将来を見据えて堤防を作るなど、より頑健な社会を作るための作業が行われます。
酵母もわれわれ人間と同じように、時間をかけながら、状況に応じた生存戦略を繰り出し、より強い酵母へと変わっていくことができます。お酒を造る過程でも、時間をかけながら発酵していくことで、以前では耐えることのできなかった高いエタノール濃度にも耐えることができるようになるのです。

(時間をかけながらエタノールに対する耐性をつけていく)
酵母の耐性を最大限引き出し、バイオ燃料へ活用
そして、現在は社会に貢献できる、バイオ燃料づくりに特化した酵母を作る研究も進めています。
少し前までは感じることのなかった地球温暖化も、ここ数年でぐっと身近な存在となり、誰もが自分ごととして捉えるようになりました。このような背景も相まって、酵母のエタノールを使ったバイオ燃料が再び注目され始めています。
トウモロコシの芯や稲わらなど、使わずに捨てられる資源を、酵母に食べさせてエタノール燃料を作るという方法を研究しており、これが実現されると酵母が地球温暖化を始め、SDGsにも貢献できる生物となり、より人類にとって必要不可欠な存在となります。
トウモロコシの芯などは、そのままだと酵母が分解できないため、糖化処理をしてから食べさせる必要があります。しかし、この糖化処理をする過程でバニリンという副産物ができてしまい、このバニリンが酵母にとっての毒物となってしまいます。バニリンが酵母の翻訳機能にダメージを与え、エタノール発酵を阻害してしまうのです。

ですので、このような発酵阻害物質に対する酵母の耐性を向上させることがポイントとなります。そのために、バニリンがどういう風に酵母に作用しているのか、また耐性を上げる遺伝子の研究を行いながら、バニリンに対して強い酵母の育種をしています。
酵母は人間と同じようにクレバーかつひたむきな生き物
今回、エタノールストレスを受けた時の酵母のふるまいについて解明することができたわけですが、それまでは、「酵母はアルコールを自ら作るくらいなんだから頑丈なんだろう」と言われていました。
ですが、事実はその逆で、酵母はダメージをしっかりと受けており、そこから酵母なりの生存戦略を懸命に繰り出しながら耐性をつけて、命を終えるまでひたすらアルコールを作り続けます。酵母は、決して初めから強いわけではないのです。
私たち人間も、初めから困難を乗り越えられる強さがあるわけではありません。困難な状況に出くわした時、追い込まれながらも、乗り越えるための方法を模索して態勢を整え、懸命に乗り越えようとします。その経験があるからこそ、将来同じことが起きてもすぐに対処ができるようになります。そして、また次の大きな困難にぶつかり、同じように乗り越えていきながら、時間をかけてジワジワと成長し、強くなっていけるのだろうと思います。

このように考えると、酵母は私たち人とよく似ているなと感心しますし、感情移入をしてしまう時もあります。
酵母の研究が楽しいのは、このような側面を持ち合わせているからでしょう。実際、酵母の研究をしているほかの先生たちも、酵母を単なる研究材料としてではなく、どこか哲学的な生物だと捉えていらっしゃる方が多いように思います。
そう考えると、私たち人間は、酵母の生き様から学べることがあるのではないでしょうか。
研究者プロフィール

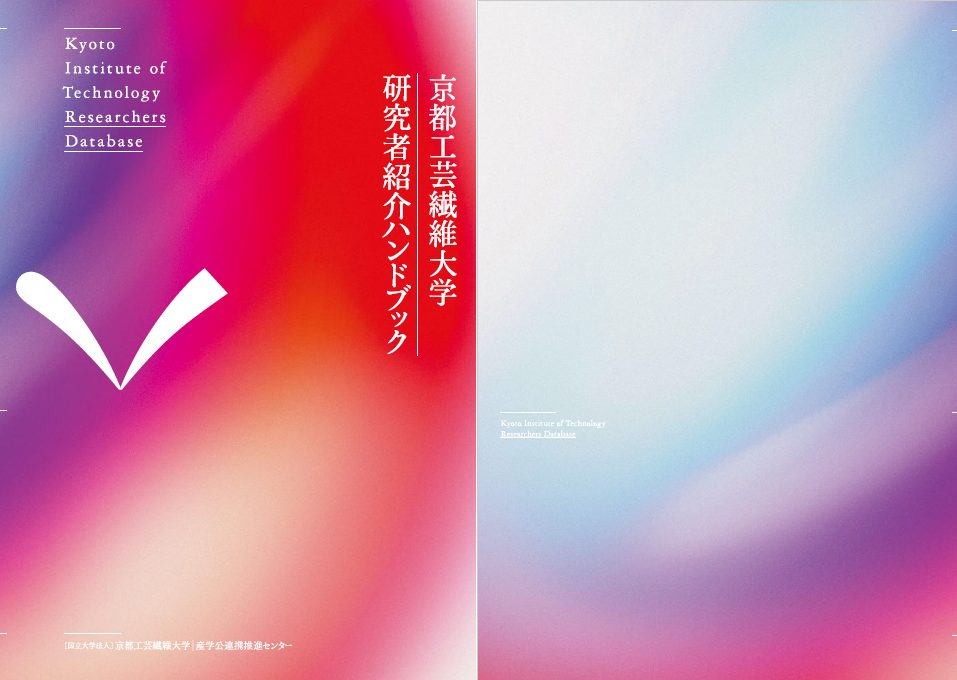
- 紹介教員を見る
研究者紹介ハンドブック
主な発表論文・関連特許
Contribution of the yeast bi-chaperone system in the restoration of the RNA helicase Ded1 and translational activity under severe ethanol stress
著者名:Ryoko Ando; Yu Ishikawa; Yoshiaki Kamada; Shingo Izawa
掲載誌名:J. Biol. Chem.
出版年月:2023年11月
Severe ethanol stress inhibits yeast proteasome activity at moderate temperatures but not at low temperatures.
著者名:Vo Thi Anh Nguyet; Ryoko Ando; Noboru Furutani; Shingo Izawa
掲載誌名:Genes to Cells : devoted to molecular & cellular mechanisms
出版年月:2023年10月
Yeast Tor complex 1 phosphorylates eIF4E-binding protein, Caf20.
著者名:Yoshiaki Kamada; Ryoko Ando; Shingo Izawa; Akira Matsuura
掲載誌名:Genes to Cells : devoted to molecular & cellular mechanisms
出版年月:2023年09月
Detoxification of the post-harvest antifungal pesticide thiabendazole by cold atmospheric plasma.
著者名:Shizu Fukuda; Yasuhiro Sakurai; Shingo Izawa
掲載誌名:Journal of Bioscience and Bioengineering
出版年月:2023年08月
Adaptability of wine yeast to ethanol-induced protein denaturation
著者名:Noboru Furutani; Shingo Izawa
掲載誌名:FEMS Yeast Research
出版年月:2022年11月
- 産学連携や研究支援に興味がある方(産学公連携推進センターHP)
- 紹介教員にメッセージを送りたい方(メッセージフォーム)
- 大学や学生を支援したい方(基金事業)
- 受験を考えている方(入試情報)
- 大学全体について知りたい方(京都工芸繊維大学HP)

